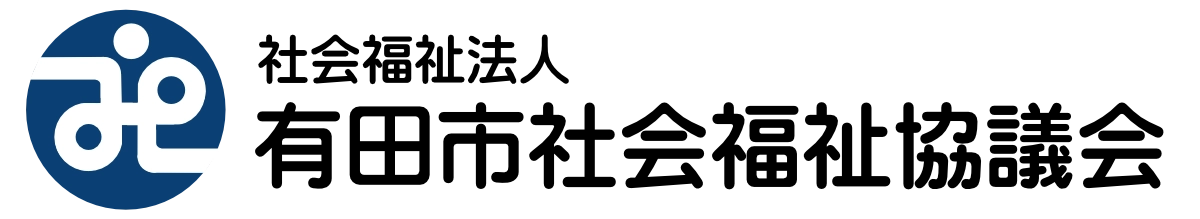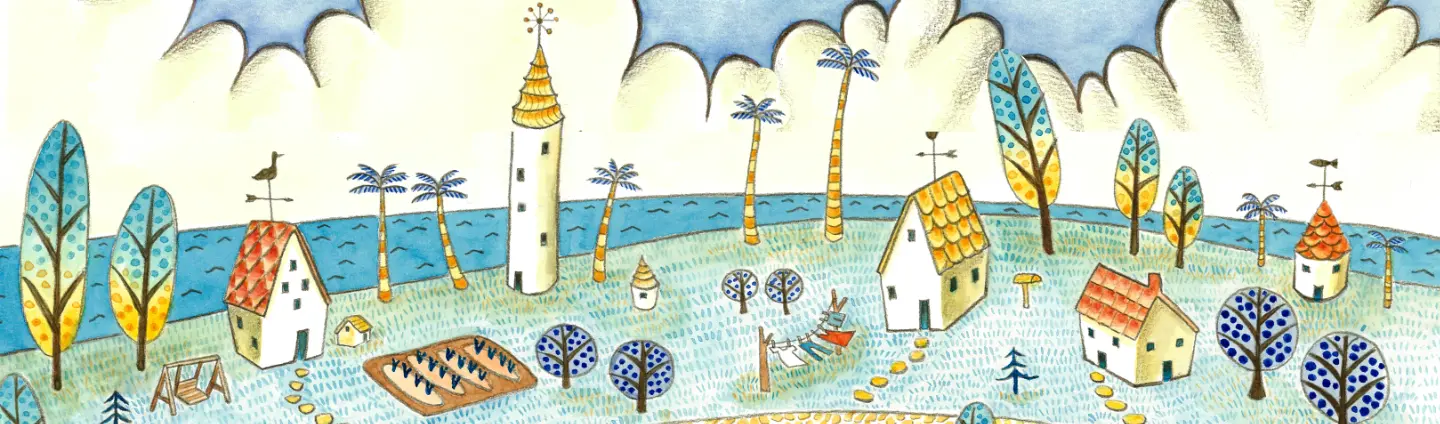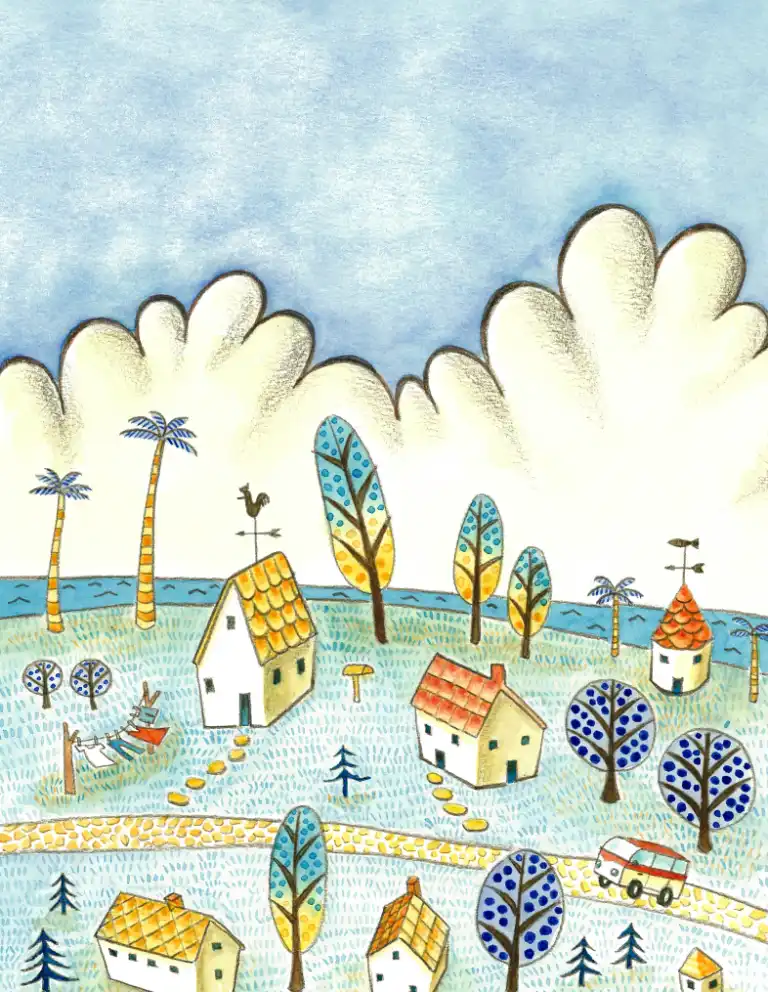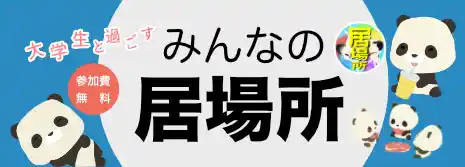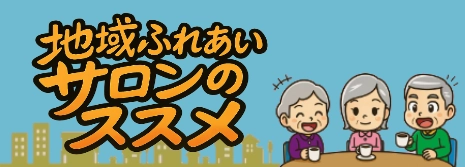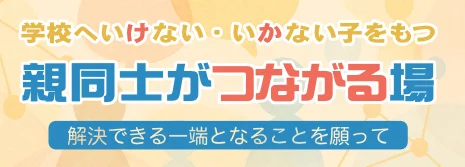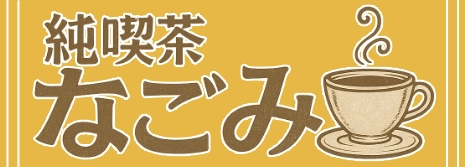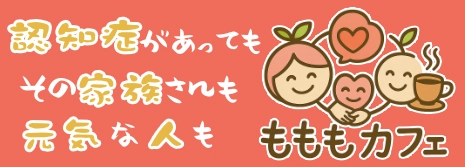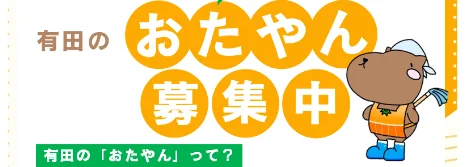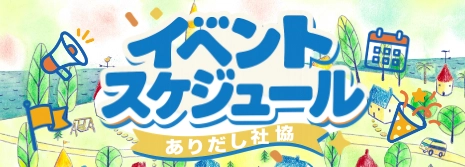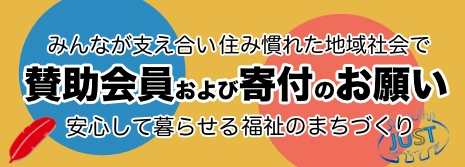10年後の恩返し授業
有田市社協が実施している「子どもたちがつなぐ未来への希望 福祉の種まきプロジェクト」は2013年度からスタートしています。当初は、社協事務所と近い宮原小学校をモデル校として、4年生以上で年間を通した地域とつながる授業を実施していました。特に6年生は、高齢者宅訪問、笑顔あふれる子どもカフェ、ふるさと交流会と学期ごとにゴール設定をして本当に1年間一緒に学んでいました。
そんな濃密な授業を一緒につくっていた先生が、今春、再び宮原小学校に戻ってこられたのです。
また一緒にやりましょう!
コロナ禍以降、同じプログラムができなくなり、部分的にご一緒する形に変わっていました。この言葉をいただき、社協としても大変嬉しく、5年生での1年間を通した授業コーディネートに入っています。多様な立場の人との出会いによって学ぶ機会をつくりだし、5年生なりに社会の一員としてできるとことを考えていきます。1学期は「認知症」について学び、当事者家族や支援者と交流しました。
そして2学期の初回交流相手は、「先輩たち」。
戻ってこられた先生が10年前に担任していた6年生たちは現在基本的には大学4年生の学年。大学生との交流を通して、少し先の未来を描くのも大事なことだと意見が固まり、卒業生たちに呼びかけました。最終的には他校のお友達を含む11人が実際に授業に入ってくれました。
やるからには本気で!いい授業を!
この先輩たち、小学校のころから主体的に活動してさまざまな取組をしてきました。その姿勢は今も全く変わらずで、授業計画の提案がたくさん出され、ちょっとそれは小学生には高度過ぎる(笑)と、こちらが軌道修正することもありました。教員と先輩と社協職員がオープンチャットで意見交換をしながら、オンラインで打ち合わせをして、何度も何度も修正をして事前事後学習と1日2コマの授業計画が完成しました(もう収まらないんじゃないかと不安になったほどです笑)。

先輩たちの学び舎は既に取り壊されています(現在の小学校校舎は中学校として過ごした場所)。
授業前に全員で打ち合わせをしましたが、全員が揃うのはこの時が初めてでした。恩師との再会にお互い笑みを見せながら、最後は「もうチャイム鳴るで〜」と小走りに教室に向かいました(笑)。

2クラスあるので、先輩たちも二手に分かれて担当制にしてじっくりお話しました。
事前に先輩の自己紹介シートを送ってあり、子どもたちはそれを見て先輩のことを想像し、質問を考えたり、先輩に伝えたいことを整理していました。子どもたちが取り組んだワークシートも先輩考案です。

東京からオンラインで参加してくれた先輩もいました!
海外に行った写真を見せてもらいながら興奮する子どもたちの様子もありました。いろんなことにチャレンジできる幅が広がるのも大学生ですよね。
先輩たちも子どもたちが興味を持てるようにと、写真や専門の道具を持ち込んだり、クイズ形式にしたりと色々工夫をしていました。

「髪の毛の色を明るくしているのは、部活の勝利を願ったゲン担ぎだよ」と子どもたちに説
明していた先輩たち。社協ワーカーとしては、それができるのも大学生の醍醐味だと思いま
す。生き生きと楽しそうに話をしている、まさしく青春を謳歌している先輩たちの体験談に触
れて、刺激を受けている子どもたちです。
後輩の気づきと学び・先輩たちのアクション
子どもたちの質問は多岐に渡っていて聞いているこちらも楽しかったです。
進学で有田市を出ている先輩が半数以上。就職は和歌山に戻ることが決まっている先輩や今後戻ると話される先輩もいました。県外就職が決まっている子も既に県外で働いている子もいます。
子どものころから宮原の秋祭りが大好きで、笛や太鼓に魅了されてきた先輩はこのまちに恩返しするために戻ってくると話してくれました。宮原小学校では現在篠笛クラブがあり、自分たちががんばっていることを自分たち以上の熱量で語ってくれる先輩に子どもたちもロックオンしたようでした。

5年生の子どもたちは、先輩が来るからと授業前の掃除の時間にそれはもう一生懸命だったそうです。机の中のものを引っ張り出して中を拭きあげる子までいたそうです(笑)。この単元では相手を思いやる気持ちを育てたいという教員のねらいもあります。先輩を迎えるために自分にできることは何かと考えて行動したのは立派な成果だと思います。
授業後、先生が子どもたちの様子を教えてくれました。
「先輩たちのような優しい人になりたい」
「秋祭り、絶対いく。また(先輩)さんと話がしたい」
「月に28万円稼いでるのにビックリした」
「私もピアノを今まで以上にしっかり練習して、中学、高校、大人になっても続けようと思った」
「新町周辺をブラブラして、また、(先輩)さんに会いたいです」
「最初から最後まで笑顔で話してくれた。とても話しやすかった」
「お菓子を作るために、細かな作業が必要なんだとわかった。(先輩)さんの作ったお菓子が食べたい」
「僕も10年後、先輩たちみたいにこの学校に戻って来たい」
「部員100名のキャプテンってすごい。私もそんなことができる人になりたい」
全員が楽しかった。また会いたい。中には緊張して質問したいことの半分も言えず、自分のコミュ力のなさを嘆いている子どももいました。今回の授業で、朧げながらも1人1人が10年後の自分自身の姿を考えることができてよかったなと思いました。
有田市社協としても初チャレンジとなった授業ですが、10年前、総合の授業で一緒に取組んだ経験がこの関係性を作ってくれたのだと感じました。先輩たちの中にも、高齢者宅訪問のことは今も強く覚えていますと話してくれる子もいました。
福祉教育は結果が見えにくいものです。宮原町という町の中で育った子どもたちが、授業を介して、また、地域の中でさまざまな人と触れ合って育ったことで、ふるさとへの愛着をもって育ってくれたことはとても嬉しいことです。
学校教育と地域の思いが同じになれば、お互いにウィンウィンになれるのだろうと可能性を感じました。その証拠に、この先輩たちはこの授業をきっかけに、宮原町のために別の形でも活動を続けたいと言っています。もちろん、そんな言葉を流したりはしません!☺v